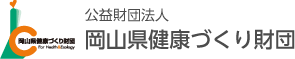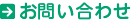私たちは、お客様からの依頼や委託により飲料水や排水、公共用水(河川・湖沼・海)などの様々な水質検査を行っていますが、そのほとんどが現地に伺って採水しています。
自然豊かな水辺が多いので、川ではフナ、コイ、アユ、スッポンなど、海ではサヨリ、イワシのほか、スナメリという小型のクジラを見かけるともあります。また、山間部ではタヌキ、シカ、イノシシ、時にはサルにも遭遇します。
採水現場によっては船に乗ったり、渓谷を歩いたりすることもありますが、職員には釣り好きが多く、自然と魚の姿を探してしまいます。
ところで、「アマゴ」や「鰻」と聞いたら、多くの方は川魚(淡水魚)と思うのではないでしょうか?
 「アマゴ」はサケ科の魚で、川で生まれて一生を川で過ごすもの(陸封型)をアマゴといい、海で生活して川に戻ってくるもの(降海型)をサツキマスといいます。
「アマゴ」はサケ科の魚で、川で生まれて一生を川で過ごすもの(陸封型)をアマゴといい、海で生活して川に戻ってくるもの(降海型)をサツキマスといいます。
そして、その姿形は大きく異なります。
陸封型のアマゴには体表に鮮やかな暗青緑色の小判型の模様(パーマーク)と朱色の斑点があり、その美しさから「渓流の女王」と称され、体長は20~30㎝程になります。
対して降海型のサツキマスは成長とともにパーマークが薄れ、体色が銀白となり、遡上するころには35~50㎝程に成長して、鼻が曲がるなど顔つきも鋭くなります。
降海型は河川から海へと棲む場所を変え、食べるものも外敵も違うなど厳しい環境で育つため、生き残る個体は少数となる一方で大型化し、沢山の子孫を残せるようになります。
 では、「鰻」はというと、海で産卵し川や湖で育つ「降河回遊魚」と呼ばれています。
では、「鰻」はというと、海で産卵し川や湖で育つ「降河回遊魚」と呼ばれています。
グアム近海のマリアナ海溝でふ化した鰻はレプトセファルスと呼ばれる透明で平べったい幼体となります。その後、体長5~6㎝程のシラスウナギに成長し、日本や中国の川を遡上します。そこからは、川(淡水)で育ったり、汽水域(海水と河川水が混じるところ)で成長するものなど、育ち方もいろいろあるようです。同じ場所で成長するものもいれば、川と海を行き来しながら成長するものもいます。また、生息域によっては体色が黒色や黄色っぽかったりするほか、岡山県の児島湾で捕獲されるものは背中が青緑色であることから「青うなぎ」と呼ばれ、食べると身や皮が柔らかで大変美味であることから希少なブランド鰻となっています。
生まれる場所が同じでも、育つ環境が変わることで容姿も変わっていくのっておもしろいですね。
未来へ、豊かで美しい自然を残すために、当財団としても引き続き自然環境の保全に寄与してまいりたいと思います。